まえがき
この話は、私が小学生の頃、友人の誰かから聞いた本当にあったかどうかはわからない話だが、わかるとゾッとする話だ。
2020年10月23日、夢に出てきて思い出したため執筆した。
聞いた話は正確には覚えていないため、加筆し、再構成して作り直した。なので、原作とはちょっと違った内容になっていると思う。似た話を知っている方、連絡いただけると嬉しい。
(文・イラスト/大嶋信之)
『山小屋のお婆さん』
ある日、一人で登山をしていた若者が、道に迷ってしまった。
空も暗くなってきたので、下山しようとするも、道がわからなくなっていた。
あせる若者。
辺りは完全に暗くなってしまった。
途方に暮れ、手探りで山中を歩いていると、遠くに灯りが見えた。

「家だ!!」
若者は救われたと思い、灯りのついた家を目指した。
近くまで来ると、平屋の家が一軒建っていた。
灯りのついた部屋を、窓からカーテン越しにのぞき見ると、
一人の女性らしき人が、奥の台所で料理をしている姿が見えた。
「助かった!」
若者はそう思い、すぐさま玄関に移動し、扉をノックして鳴らした。
「ドンドン!」
しかし、誰も出てこない。
「おかしい」
そう思い、ノックを何度か鳴らした。
「ドンドンドン、ドンドンドン!」
それでも、誰も出てこない。
「すいません! 登山をしていたら、道に迷ってしまって。」
若者は大声で叫んだ。
「・・・」
しかし中から何も返答がない。
「仕方ない」
若者は、扉を開けようと、ドアノブに手をかけた。
扉には鍵がかかっていて、開かなかった。
若者は、ドアノブの下に小さな鍵穴があるのを見つけた。

若者は、鍵穴から中を覗いてみた。
「ん? 赤い。何も見えない。」
何も見えない。「真っ赤」で何も見えない。
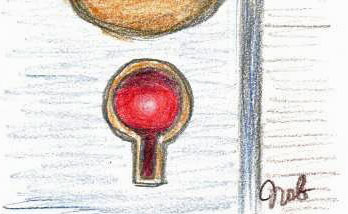
鍵穴に目をくっ付けて家の中をよく見ようとするも、とにかく真っ赤で何も見えない。
部屋の中は灯りがついているのに、何度見ても不思議と鍵穴の向こうは「真っ赤」で何も見えないのだ。
若者は、再び窓から中を伺った。
すると先程の女性は台所にはいなくなっていた。
「さっきは見間違えたか、留守だったのかもしれない。」
若者は、このまま下山しても迷うだけだからと、この家に誰かが帰ってくるのを待つことにした。
扉の前で、座りこんだ。
たまに、鍵穴をのぞき見るも、毎度「真っ赤」で何も見えない。
灯りのついた部屋の中もカーテン越しに確認するが、やはり誰もいないようだった。
そんなことを繰り返しながら、一睡もする間もなく、夜が明け東の空が白んできた。
結局、その家に誰も帰ってくることはなかった。
周囲が明るくなったところで、若者は下山することに決めた。
その家を後にするとき、もう一度鍵穴を覗き込むと、やはり真っ赤で何も見えなかった。
窓から中を覗いても、誰もいないようだった。
「なんて、不思議なんだ。」
若者は思った。

家を後にし、下山を始めた。
「あの家は、何だったのだろう?」
そう思いながら、歩いて登山道を探した。
少し迷うことはあったが、明るくなったおかげで、無事に登山道に出ることができ、下山することができた。
不思議に思った若者は、何人かの登山仲間に、その家の話をした。
すると、その家を知っているという一人の登山家がいた。
「ああ、その家なら知っているよ。一人の婆さんが暮らしている。」
続けて、その登山家が言った次の言葉を聞いて、
若者の背中が凍りついた。
「でもさ、
不思議なんだよ。
その婆さんの目、いつも真っ赤なんだよ。」

おわり。
Nobuyuki Oshima(大嶋 信之)
・プロフィール
Email
info@nobart.com
Follow me

サイトインフォメーション
ページカテゴリー
ブログ(投稿記事)カテゴリー
- Maia Surf Island(マイア サーフアイランド)
- 星
- AI(人工知能)
- 海
- 天然温泉の銭湯
- アクセサリー
- 月
- 米作り(コメづくり)
- テーマパーク
- UFO撮影画像
- UFO、宇宙人
- 禁酒日記
- コラム・エッセイ
- 絵画、イラスト
- アート(Art)
- スケートパーク
- サーフィン
- ブログ(投稿記事)一覧
- スケボー(スケートボード)
- 薪で湯を沸かしてる銭湯
- 靴・シューズ
- キャラクター
- 山
- 天然温泉
- オカルト情報・研究、体験談
- 私が経験した不思議体験
- 医学・医療
- 植物
- ダンス
- 絵本、漫画
- 海水浴
- 壁画アート(銭湯の絵・絵画・ペンキ絵師)
- 知人が経験した不思議体験
- スポーツ
- 動物
- 電車
- 銭湯仲間
- 心霊・怪奇現象・怪談
- ファッション
- 造形
- 量子科学・量子コンピュータ
- 東京都
- 海外
- 写真アート
- 空
- スピリチュアル
- トレーニング
- 物理科学
- 埼玉県
- 音楽
- 宇宙
- 自然
- 夢日記
- 神奈川県
- 農業・畜産・酪農
- 絵の描き方
- NFT
- 銭湯めぐり
- 千葉県
- 文芸・文学
- 栃木県
- 日記・レポート
- 群馬県
- お知らせ
- 知人の作品
- 茨城県
- お店(ショップ)
- 福島県
- 公園
- 長野県
- 神社、お寺、宗教
- お祭り
- イベント
- 観光
- 子育て
- メディア掲載・出演、展示、タイアップ利用など
- 新商品、製品開発など
- 動画
